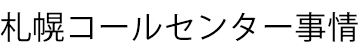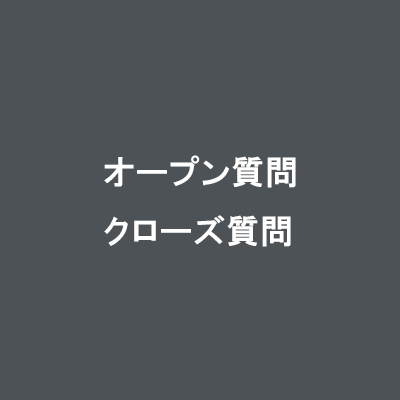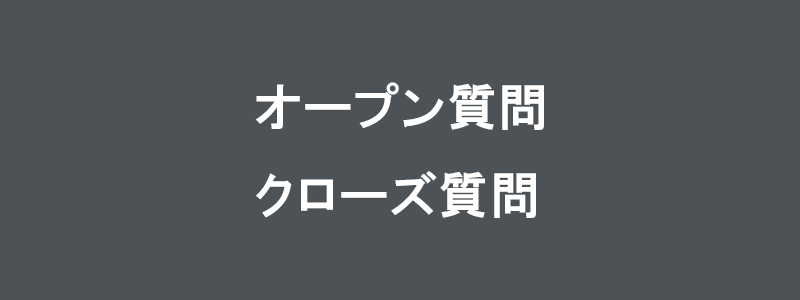
「オープン質問」「クローズ質問」の解説です。
「カウンセリング」から生まれたオープン質問、クローズ質問。
「オープン質問」「クローズ質問」とは、カウンセリングから生まれた質問の技法。
1960年代半ばに、基本的なカウンセリングと面接のスキルを教えるための方法論として、アレン・E.アイビイ教授が開発した「マイクロカウンセリング」で扱われる質問のテクニックです。
原文の英語では “Open question, Closed question”とあり
国内では「Open question」は「オープン質問」「開かれた質問」、
「Closed question」は「クローズ質問」「閉ざされた質問」の翻訳名称でも知られてます。
2つの使い分けとして
「オープン質問」は相手が「どう思っているのか」や「どのような状況にあるのか」「ほしいものは何か」など自由に回答できる質問。
「クローズ質問」は名前や性別、生年月日や住所など、答えが決まっている質問。
相手に「はい」「いいえ」の回答を求める質問です。
オープン質問は自由に答えてもらう質問、クローズ質問は決められた回答を求める質問。
質問には2つの基本的な形式があり、「オープンな質問」または「クローズな質問」のいずれかです。
「オープンな質問」はクライエント(相談者、来談者)の回答が言葉少なにならないように、もっと広範囲の答えが帰ってくるよう導いていきます。
オープンな質問の例「高校を卒業した時、あなたはどう思いましたか?」
一般的にその質問はwhat、how、why、または、couldからはじめます。
一方「クローズな質問」は通常、クライエントが1つの単語もしくは、ひと言の返事といった、より限定的な回答をするように導く傾向があります。
クローズな質問の例「今年の秋、大学に入学しようと思っていますか?」
その質問形式はis、are、doからはじめます。
マイクロカウンセリング:多文化世界での技能訓練の実施:アレン・アイビイ(著)より。
クローズ質問でリズムをつくり、 オープン質問で深い話を引き出す。
- まずは相手が答えやすい質問を
- 関係性ができたら意見を引き出す
- 答えにくい質問は訊き方を工夫する
20代でマスターしたい仕事のルール「考え方・伝え方」のきほん:HRインスティテュート(著)より
まず対話のはじめには、イエス・ノー、または数字や固有名詞などの単語で答えられる質問をするほうが安全です。こうした質問をクローズド質問と言います。
「残業は多いですか?」「出身はどちらですか?」「今の社員数は?」というのがクローズド質問です。
そして、だんだん会話のキャッチボールができて、相手からもっと自由に情報を得たいとき、単語だけでは答えられない質問に切り替えるようにしていきます。こうすることで話が広がります。
たとえばビジネスでは、「この商品についてどう思いますか?」「お仕事の状況はいかがですか?」など。
プライベートでは「最近元気がないけどどうしたの?」「この間の海外旅行どうだった?」といった、一言では答えにくい質問です。これをオープン質問と言います。
あまり親しくない関係なのに、「〇〇についてどう思う?」といきなりオープン質問をしても、相手は答えづらいものです。これでは当たり障りのない返答になりそうですよね。
関係の浅い方には、クローズド質問で相手の答えやすさに配慮をしましょう。
「それどこで買ったの?」「土曜と日曜どっちがいい?」のような質問なら、すぐに答えられるでしょう。
そしてもっと相手の意見や本音を聴いても大丈夫と思ったときに、オープン質問に踏み込みます。
「はい、いいえ」を求めるクローズ質問、「具体的に」はオープン質問
クローズ質問では、お客様に求める答えは原則的に「はい」「いいえ」の端的な表現ですみます。そのため口下手な相手にも負担をかけず、会話が手際よく進むので、スピーディーにクレームなどの詳細を明確にしたいときには最適です。
しかし、相手にとって気の乗らない質問がつづくと、いつの間にか会話がストップすることもあるので注意が必要です。
プロフェッショナル電話力・話し方 聞き方 講座:恩田昭子(著)
「クローズ質問とオープン質問を使いこなす」より
それに対して「オープン質問」は「具体的にはどのような内容でしょうか?」というように、お客様に自由にかつ具体的に話してもらうことを目的にする質問方法です。
この方法は、質問に答える側にストレスはかかりませんが、対応する側が質問をコントロールしないと時間がかかりすぎたり、論点がずれる可能性があるので注意が必要です。
しかし答える側の自由度が増すので、本音や意見を聞き出すときなどには有効です。
「自由」なオープン質問、「確認」のクローズ質問
1 お客様が自由に話せる「オープン質問」
お客様の回答を選択肢で絞り込まず自由に話せるようにするのがオープン質問です。
これを使うと、事実と併せて、お客様の感情を引き出しやすくなります。
お客様に選ばれる人がやっている・一生使える「接客サービスの基本」:三上ナナエ(著)
「これで安心!クレーム応対6つのステップ」より
注意点としては、たくさん話していただきやすい分、お客様の話が飛んだり、長くなることもあるので、お客様の話の切れ目をうまく掴んで確認や別の質問などをいれるなどしていきましょう。
2 事実を確認しやすい「クローズ質問」
お客様がYESかNOで答えることができるのがクローズ質問です。クローズ質問を使うと焦点を絞り込んだ質問ができ、事実を確認しやすいうえに、お客様には「自分の話を理解しようとしてくれている」という気持ちになっていただけます。
注意点としては、クローズ質問の際、簡潔に答えやすい分、本音が引き出しにくく一方的になりがちです。
またそれが続くと尋問のように聞こえてしまったりもします。「2、3お伺いしてもよろしいでしょうか」と許可を得て、
- 恐れ入りますが
- 念のための確認ですが
- 失礼ですが
などクッション言葉を使いながらお伺いしましょう。
コールセンター用語集|「あ」行|「か」行|オープン質問とクローズ質問