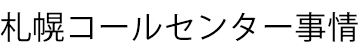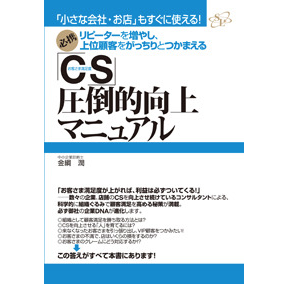金綱 潤(著)
すばる舎
本の詳細
「サービスは、結局は現場の担当者次第」
と思い込んでいる経営者は少なくないのですが、
最初にそこが間違っています。サービスの質は、個人の資質レベルではなく、
会社全体の「しくみ」が創り出すものです。
本書で考えていくCS向上のゴールは、
お客さまの喜びではありません。
そこはあくまで通過点。そのあとお客さまに、
- 再購入/再利用していただく(リピート)
- より多く購入/利用していただく(頻度とボリュームアップ)
- よい口コミを多くの方に伝えていただく(拡散)
という3つのことを最終目的としています。
CS向上とは、この3つのような
目にみえる経済的果実をあげ、
それによって経営を安定・向上させるための科学です。
そのことを強く認識してください。
したがって、一部スタッフが時限的に取り組む
啓蒙活動的なものではなく、経営者主導の下で行なう、
全体的・継続的事業なのです。
- 組織として顧客満足を勝ち取る方法とは?
- CSを向上させる「人」を育てるには?
- 来なくなったお客さまを引っ張り出し、VIP顧客をつかみたい!
- お客さまの不満で、店はいくらの損をするのか?
- お客さまのクレームにどう対応するか!?
この答えがすべて本書にあります。
「お客様満足度が上がれば、利益は必ずついてくる」
と著者は語ります。
リピーターを増やし、
上位顧客をがっちりとつかまえる方法。
ニッカウヰスキー、ニチレイにて
営業、マーケティング統括、新規事業開発に携わり、
現在はコンサルタントとして
数々の企業、店舗のCSを向上させ続けている
著者が伝授する、
科学的に顧客満足を高める秘策が満載です。
小さな会社・お店でもすぐに使える方法を
「元気な中小企業」の成功事例をもとに解説しています。
目次
第1部 CS基礎知識編
序章 今のご時世、生き残りにはCSしかないでしょう
1 CSは、主観ではなく「科学」である
CSは、経営者主導で取り組むべきもの
「箱根駅伝」のブランド力に学ぶ
2 自社すみずみまでCS向上を浸透させよう
売上・利益と関連づけて考えよう
CSの実現の難しさ
十人十色の顧客評価をどうとらえるか
3 「お客さま」を知り、自社をも知ろう
「お客さま目線」とは何か
サービスを利用するのは「問題解決」のため
自社の魅力を正確にみきわめよう
客商売が満たすべき「3つのA」
4 時代に即したCSを「開発」しよう
ひと手間かけないと売れない時代
付加価値の創出に頭をひねろう
・利用ガイド こんな人は本書のココを読め!
第1章 CSとは何か 初級編 まずは興味をもとう
1 CSは、お客さま主導で日々進化している
CSを定義する難しさ
CSのこれまでの進化プロセスを知ろう
CSの存在目的
お客さま目線で検証する習慣づけ
2 企業のCSをとりまく現状
コスト高・情報化・複雑化
How to do から、What to do へ
各企業の取り組みや習熟度はまちまち
CS認識にギャップが生じる背景
CSに無関心な企業はどれだけ損をするか
3 CSは経営を救うのか? CS向上とコストの関係
投資すればするほどCSは上がっていくのか
業績向上に結びつける、CSコストのかけ方とは
4 CS追求で得られるメリットなどを知ろう
CS追求の過程で得られる4つのメリット
狙うべき「お客さま像」を具体的に考える
お客さまの潜在的な「願望や期待」を理解する
お客さま目線にに立ち、自社の「ライバル」を発見する
「顧客との接点」への意識を高める
5 CSの達成をさまたげる要素
CS追求そのもの目的化
目的の共有化の遅れ
目的設定がうまくいっていない
第2章 CSとは何か 本編 メカニズムをじっくりと学ぼう
1 CSとは、頭をたくさん使うもの
CS視点からみる、成長企業と不振企業
経営もCSも「サイクルを回すこと」
CS向上サイクルを回そう – ステップ別留意点
2 CS向上に欠かせない人材スキルとは
お客さまを理解する力
お客さまが満足する理由を把握する力
お客さまが満足するアクションを実際にカタチにする力
3 「問題解決力」を体得しよう
お客さまの関心事や重視点をつかむには
ケータイの機種を選ぶ際の重視点
お客さまが選択する瞬間を見逃すな
商いに勝つ、3つの勝負どころ(顧客接点)
4 3つのAのイメージをつかみ、お客さま目線を自分のものに
Availability – 使い勝手をよくしよう
Accessibility – 欲しいとなったらすぐ欲しい
Affordability – だれしも気になる損得勘定
5 ターゲット顧客を絞り込む
ターゲットを明確にするメリット
ターゲット設定における考え方
サービス設定、利用TPOを絞り込む
計画を検証する
6 「購買心理」をとことん考えてみよう
「割に合わない」ことは悪いことか?
「並」で終わらないための意外な秘訣
割に合わないサービス、挑戦も悪くない
第3章 スタッフパワーがCSを創る
1 従業員が不満だらけだとどうなるか
CSを創るのは、ほかでもない「人」
「お客様は神様です」は真実か
CS < ES
2 待遇に不満な従業員に対してのアプローチ
従業員は何に不満を抱くか
待遇整備より「育成」が急務
OJTの進め方
3 ESの充足度をどのように高めていくか
職場生産性から推し量る
逆ピラミッド組織を目指そう
非正規従業員の力を引き出す
共通言語をもち、一人一人の労働観をつかむ
4 現場における人づくりの勘所
EQが高い人材を育てる
マニュアル詰め込み成果主義の弊害
新人育ては啓蒙から
新人育ては見守りとサポート
適切な目標を設定し、「燃やして」やろう
5 What to doが考えられる人を育てよう
自律的人材がCSを創る
第2部 CS調査編
第4章 CS調査のさまざまな手法
1 お客さまの隠れた本心を科学的に引き出そう
お客様の声は値千金
間違いだらけのCS調査
2 実施上の留意点
商品・サービスの購入などについてのCS調査
接客対応についてのCS調査
量と質の両方が問われる
3 調査にあたり、ふまえておきたいポイント
お客さまは本当のことなど話してくれない
事前にすべき検討
4 いろいろなCS調査方法(1)紙を用いた調査
メリット
デメリット
紙の調査における注意点
5 いろいろなCS調査方法(2)ネット調査
メリット
デメリット
ネット調査を上手に使いこなすには
6 いろいろなCS調査方法(3)電話調査
電話調査の概要
サンプル数・不能票数の報告(実査管理)
外部委託せず、自社で実施するには
電話調査オペレーターの心得
7 いろいろなCS調査方法(4)面接調査
集団面接法
討議の準備とモディレーターの役割
詳細調査法
Methods ‘覆面調査’を知っていますか
第5章 CSは中小企業を元気にする
他社事例に学び、CSを楽しもう
1 CS視点から「商機」をつかもう
業種と業態
最近支持を受けているビジネスの例
元気な中小企業
(1)すみずみまでたべたい!マグロへの愛情でひた走る「三浦三崎のマグロ屋さん」
(2)受け身から発信に転じ、見事に息を吹き返した伝統工芸「小田原のからくり細工」
(3)漁業者の問題解決を自社再成長の起爆剤にした「一度は泊まりたい料亭旅館」
2 注意!(1)お客さまがホンネをいいづらい「教育産業」
「センセイ」には文句もいえない
ネットリサーチで噴き出る不満
教育産業に欠かせない4つのCSアクション
3 注意!(2)フォローが決め手の「ネットショッピング」
近年の激戦業界
既存顧客へのアフターフォローのポイント
新規ユーザー開拓のポイント
第6章 お客さまアンケート 効果的な実施方法
1 全業種対応の基本設問 利用上のポイント
質問法による調査に用いる
基本設問のポイント
2 業種別調査項目設定ポイント 作成の意図と活用方法
B to Bか、B to Cか
B to BとB to Cの相違点
B to Cにおけるアンケートの考え方
B to Bにおけるアンケートの考え方
第7章 CS調査 実施における注意点
1 ホンネを拾い、お客さまの心の裡(うち)を知ろう
お客さまの状況を細かく区切って想定する
お客さまは意外と後ろ向き
2 CS調査の実務を知ろう(1)調査設計
意外と難航する、調査目的の明確化
調査設計におけるポイント
実施する – いつ、どこで、だれが?
3 CS調査の実務を知ろう(2)実務分担
調査前〜調査本番の実務
調査後の実務
4 CS調査の実務を知ろう(3)アンケートの各種手法
記名式と無記名式の違い
アンケート報償の考え方
アンケート回答の回収
5 関係者すべての「納得」や「理解」が調査品質を高める
調査における「よくある質問」
調査対象者から寄せられる質問
調査項目に関する質問(質問への質問)
調査担当者から寄せられる質問
天候等外的要因による調査継続の判断に関する質問
実査中に判明した問題点
6 NG事例に学ぼう(よくないアンケート調査実例)
実施におけるNG事例
結果分析におけるNG事例
第3部 CS経営改善編
第8章 お客さまの「声なき声」を感知しよう
1 悪い結果の上手な受け止め方
クレームをどうとらえ、受信していくか
満足・不満足の構造を知ろう
2 読み取った結果をスタッフ間で共有するには
共有のための訓練や手法
チームワークも品質のうち
3 顧客との接点を考える
顧客接点のメカニズム
顧客接点のマネジメントの手法
相反視点への配慮がお客さまとの関係を醸成する
4 結果や現象の本質的意味を掘り下げる
クレームの意味を読み取ろう
アンケートの意味を読み取ろう
お客さまの要望を読み取ろう
サービス業は評価には坑えない
第9章 CSのための経営改善(1)
「よくある問題」をクリアしていこう
1 いろいろな調査視点と結果の活用(1)集客の波を安定させよう
集客の波をなくすには
休眠客への3つのアプローチ
2 いろいろな調査視点と結果の活用(2)お客さまの不満を定量化しよう
口コミの伝播力を考えてみる
不満の程度と事前期待の関係
顧客の不満実態の「見える化」を図る
3 いろいろな調査視点と結果の活用(3)財務諸表上のCSコストを読み解こう
損益計算書上のCS向上費用
貸借対照表上のCS向上費用
財務諸表ではみえづらい、CS向上への投資効果
CS向上のための経費管理の具体例
財務諸表には表れない、CS向上活動の効果
4 いろいろな調査視点と結果の活用(4)上位顧客を満足させる「コト」とは
なぜ、上位顧客を目標にすべきなのか
上位顧客のおメガネにかなうのは難しい
上位顧客はサービスを超えた「ホスピタリティ」を求める
お客さまと企業、思いはとかく食い違う
5 改善に向けての課題整理 空間稼働率アップへの取り組み
生産と消費の同時性
料亭のイメージを再検証する
中心課題を整理する
問題を構造化するだけで解決に一歩近づく
第10章 CSのための経営改善(2)
経営者への5つの指針
1 CS指針(1)経営者が堅持すべき基本姿勢とは
判断力・見識が問われる時代
「姿勢」が「見識」を支える
CS方針の指令の落とし方
2 CS指針(2)トップ営業のすすめ
今すぐできる、トップ営業
企業イメージの管理はトップにしかできない
3 CS指針(3)定期的に推進組織の機能チェックを
組織を「診る」ポイント
メンバー間の闊達なコミュニケーション
4 CS指針(4)定期的に実施計画の進捗チェックを
スケジュール設定について
もう一つのPDCAサイクル
真の問題発見力を身につける
5 CS指針(5)CSへの取り組みの対外的アピールを
なぜ、取り組みをアピールすべきなのか
アクション事例 – 過剰品質の見直し
6 21世紀のCS – お客さまが本当に望む価値とは
リクエストに応えるだけがCSか
21世紀は、「企業としての良心」を追求する
付録 巻末資料
CSアンケート
・基本設問
・業種別 調査項目設定ポイント

金綱 潤(著)
すばる舎